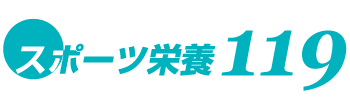運動後の疲労感や翌日まで続く身体の重だるさは、一般的に「乳酸がたまっているから」と説明されることが多いのですが、乳酸そのものは直接の疲労物質ではありません。
現代のスポーツ科学では、運動による疲労の真の原因は「身体のpHバランスの変化」と「微細な炎症」にあることが明らかになっています。しかし、多くの運動習慣者がこの事実を知らないまま、疲労回復を試みているのが現状です。
今回は、乳酸と疲労の関係性、そして効果的な疲労回復方法について詳しく解説します。
Contents
そもそも乳酸とは?
私たちの身体は運動するとき、主に「糖」と「脂肪」をエネルギー源として使い分けています。
筋力トレーニングや短距離走などの高強度な無酸素運動では、瞬発的に大きなエネルギーが必要となるため、効率良くエネルギーを生み出せる糖を主な燃料として使用します。
乳酸は、この糖からエネルギーを作り出す過程で生まれる副産物です。
一方、ジョギングやウォーキングなどの有酸素運動では、主に脂肪を代謝してエネルギーを作り出すため、発生する乳酸の量は比較的少なくなります。脂肪の代謝には十分な酸素が供給されるため、糖の無酸素的な分解が起こりにくいからです。
「きつい」と感じる高強度の運動ほど乳酸が発生しやすく、軽めの有酸素運動では乳酸の発生は抑えられます。
乳酸がたまるメカニズム
「運動後の疲労感は乳酸が原因」という話を聞いたことがある方も多いでしょう。
しかし、実際に体内で何が起こっているのか、詳しく理解している方は少ないかもしれません。運動時の乳酸の動きを正しく知ることで、効果的な疲労回復につなげることができます。
肝臓での処理が間に合わなくなると蓄積される
乳酸は体内で常に生成されており、通常は肝臓で適切に処理されます。しかし、激しい運動をすると処理能力を超えた乳酸が蓄積されることがあります。
体内で作られた乳酸は血流に乗って肝臓へと運ばれ、そこでエネルギー源として再利用されたり、他の物質に変換されたりします。ところが、高強度の運動を行うと筋肉での乳酸産生量が急激に増加し、肝臓での処理能力を上回ってしまいます。
この処理が追いつかないと、血中の乳酸濃度が上昇し、一時的に体内に乳酸が蓄積された状態となるのです。
ただし30分~1時間で血中濃度は下がる
運動で蓄積された乳酸は、思っているよりもずっと早く体内から処理されます。健康な人であれば、運動後30分から1時間程度で血中乳酸濃度は正常値に戻ります。
運動によって一時的に血中濃度が上がった乳酸は、実は「疲労物質」として体内に残り続けるわけではありません。
むしろ、蓄積された乳酸は再びエネルギー源として有効活用されるため、発生から30分ほど、長くても1時間以内には通常の数値まで下がります。
特に疾患などがない限り、血中の乳酸濃度が高いまま維持されることはありません。
このことから、運動後数時間から数日続く筋肉の疲労感や重だるさは、乳酸の蓄積以外の要因によるものと考えられています。
乳酸がたまる問題は「身体のpHバランスが崩れること」
最近の研究では乳酸自体が直接的な疲労物質ではないことがわかってきています。
なぜ運動後に疲労を感じるのでしょうか。その答えは、身体のpHバランスの変化にあります。
「身体のpHバランスが崩れる」とはどういうこと?
私たちの身体は、pH値7.35〜7.45という狭い範囲の弱アルカリ性に保たれています。この微妙なバランスが、私たちの健康状態に大きく影響しているのです。
通常、pH値は日常のさまざまな刺激によって変動しますが、腎臓や胃腸、呼吸機能などによって自動的に調整されています。
しかし、血中の酸が増えすぎてpH値が下がったままになると、疲れやすくなったり、肌トラブルが現れたり、免疫力が低下したりといった不調が生じます。
乳酸はその名の通り「酸」の性質を持っているため、激しい運動によって大量に発生すると、身体が酸性に傾いてしまうのです。おおよそ6〜6.5程度までpH値が下がるといわれています。
運動後に感じる疲労感や身体の重さは、実はこのpH値の変化によって引き起こされているのです。
ミネラル不足ではよりpH値の調整力が低下する
身体のpHバランスを整えるために重要な役割を果たしているのが、カリウム、カルシウム、マグネシウム、ナトリウムなどのミネラル類です。
これらのミネラルは体内でアルカリ性を示すため、酸性に傾いた身体を中和する働きがあります。
さらに、ミネラルには糖代謝をサポートする機能もあり、実は乳酸を再びエネルギー源として利用するプロセスにも必要不可欠なのです。
しかし、日本人の多くはミネラル不足の傾向にあるといわれており、運動で汗をかいた状態では、さらにミネラルが失われてしまいます。
このような状態では、運動中に発生した乳酸の再利用が効率良く行われず、結果として身体に蓄積しやすくなります。そして蓄積された乳酸によって身体が酸性に傾き、疲労感や不調を感じやすくなってしまうのです。
運動パフォーマンスを向上させ、疲労回復を早めるためには、適切なミネラル補給が欠かせません。
【補足】翌日も残る疲れの正体は「微細な炎症」
翌日や数日後まで続く身体のだるさや重さを感じたことはありませんか。この長引く疲労感の原因は、乳酸の蓄積だけでは説明できません。
実は、運動によって身体の各部位で発生している「微細な炎症」が、私たちの体調やパフォーマンスに大きな影響を与えているのです。
具体的には、運動中は筋肉に負荷がかかることで、必然的にダメージを受けています。
このダメージが強くなると筋肉痛や肉離れといった症状として現れますが、痛みを感じない程度の軽微なダメージであっても、身体の各部位では微細な炎症が起こっているのです。
炎症が起こると身体は酸性に傾きやすくなり、それによって疲労感が増大し、全体的なコンディションが低下してしまいます。
結果として、普段のトレーニングで発揮できるはずのパフォーマンスが出せなくなったり、日常生活での活力が減退したりといった影響が現れます。
この炎症による疲労は、単純な休息だけでは完全には解消されないため、適切なケアと栄養補給によって炎症を抑制し、身体のpHバランスを整えることが重要です。
筋肉疲労の予防・軽減におすすめの方法
運動後の疲労感や翌日まで続く身体の重さを解消するためには、単に休息を取るだけでは不十分です。最後に、効果的な疲労対策を4つ紹介します。
トレーニング前~後のミネラル摂取
運動時の疲労を最小限に抑えるためには、適切なタイミングでのミネラル補給が欠かせません。
具体的には、運動前、運動中、運動後の3つのタイミングで摂取することが重要です。特に持久系の運動では、汗で流出するミネラルを包括的に補給できる総合ミネラルサプリメントの活用がおすすめです。
▼おすすめサプリ
「汗で流出するミネラルを丸ごと補給」できる持久系の総合ミネラルパウダーです。
トレーニング前~後のアミノ酸の摂取
筋肉疲労の回復を促進するためには、アミノ酸の摂取が重要です。
特に必須アミノ酸に含まれるBCAA(分岐鎖アミノ酸)は、運動時のエネルギー源となり、筋肉の分解を抑制し、疲労回復を効果的にサポートします。
▼おすすめサプリ
EAA(必須アミノ酸9種)を含む疲労回復に役立つサプリメントです。
推奨する摂取タイミング:「トレーニング前や競技前」「トレーニング中や競技中」「運動終了から1時間後」
ウォーミングアップとクールダウン
適切なウォーミングアップとクールダウンは、疲労予防と回復促進の基本です。運動前のストレッチや軽い体操によって筋肉を温め、血行を促進することで筋肉の柔軟性を高め、ケガや疲労を効果的に予防できます。
運動後のクールダウンでは、軽い運動やストレッチに加えて、コラーゲンの摂取も疲労回復に大きな効果をもたらします。
コラーゲンは筋肉の保水力を高め、柔軟性の向上や疲労回復をサポートする働きがあります。
▼おすすめサプリ
4つの線維たんぱく質(靭帯・腱・筋膜・軟骨・骨成分)を含むサプリメントです。
推奨する摂取タイミング:「運動前」「運動後」「就寝1~2時間前」
充分な睡眠
激しい運動後の疲労回復では、質の高い睡眠が重要です。
睡眠中には筋肉の修復プロセスが活発化し、成長ホルモンが分泌されるため、十分な睡眠時間を確保することが疲労回復に不可欠です。
運動を継続的に行う方は、1日7〜9時間の質の高い睡眠を心がけましょう。
まとめ
運動後の疲労感の真の原因は、乳酸そのものではなく「身体のpHバランスの変化」にあります。大量に発生した乳酸によって身体が酸性に傾くことで、疲れやすさや体調不良が引き起こされるのです。さらに、多くの日本人が抱えるミネラル不足は、このpH調整機能を低下させ、疲労を長引かせる要因となっています。
効果的な疲労対策としては、トレーニング前後のミネラルやアミノ酸の摂取、適切なウォーミングアップとクールダウン、そして質の高い睡眠が重要です。
正しい知識を身に付けて、より効率的で快適な運動習慣を続けていきましょう。