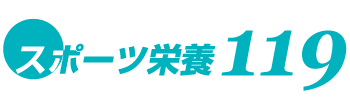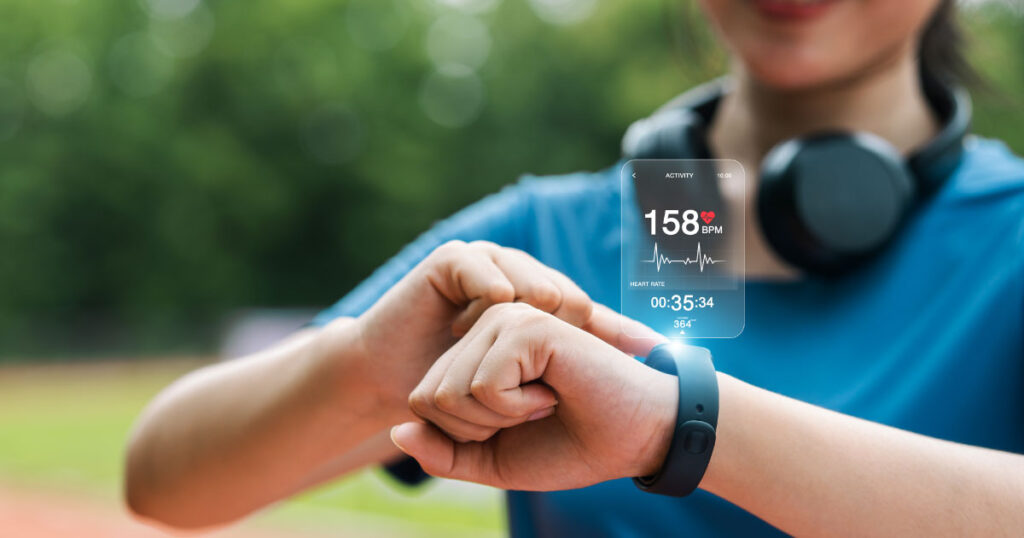マラソンで理想のタイムを目指す上で欠かせないのが「ペース配分」です。スタートから無理をすれば失速し、抑えすぎれば目標を逃してしまいます。では、初心者から上級者までどのようにペースを組み立てれば良いのでしょうか。
今回は、マラソンにおける適切なペース配分と、その維持に役立つトレーニングや栄養管理について解説します。
マラソンの適切なペース配分とは?

マラソンで理想のタイムを達成するには、ペース配分が重要です。まずは、マラソンにおける適切なペース配分について解説します。
ベストなペース配分はランナーによって異なる
すべてのランナーに共通する正しいペース配分は存在しません。走力やスタミナ、得意な走り方はランナーごとに大きく異なるためです。
自分の走力特性を把握することで、自身に最適なペース配分が見えてきます。普段の練習から自分がどのペースで何キロ走れるのかを記録し、得意な走り方を把握しておくことが大切です。
1km7分のペースが最初のステップ
マラソン初心者がまず目指すべき目標は、1kmあたり7分のペースで30分間走り続けられるようになることです。このペースはフルマラソンを5時間以内で完走する「サブ5」のペースに相当します。
30分走れるようになったら、徐々に時間と距離を延ばしていきましょう。走力がついてきたら、サブ4を目指すなら1kmあたり約5分41秒、サブ3なら約4分15秒というように、目標に応じてペースを調整していきます。日頃のトレーニングで自分の走力を確認し、無理のない目標設定をしましょう。
「イーブンペース」がポイント
マラソンのペース配分には主に3つのタイプがあります。スタートからゴールまで一定のペースを保つ「イーブンペース」、前半を速く走る「ポジティブスプリット」、後半にペースを上げる「ネガティブスプリット」です。
初心者には、イーブンペースが最も取り組みやすくおすすめです。余裕を持った一定のペースで走り切ることで、完走の確実性が高まります。
マラソンで理想のペースを維持するトレーニング

目標とするペース配分を本番で維持するには、日頃からそのペースで走れる身体づくりが不可欠です。ここでは、マラソンのペース配分を維持するために効果的なトレーニング方法を解説します。
ランニングフォームを整える
無駄な体力消耗を防ぎ、安定したペースで走り続けるには、正しいランニングフォームを身に付けることが重要です。
上半身は、身体の軸をまっすぐに保ち、軽い前傾姿勢を心がけましょう。腕は肘から90度またはそれ以上鋭角にたたみ、肘から後ろへコンパクトに振ります。肩甲骨を背骨に寄せる感覚で胸周りを少し開くと、力まずスムーズに腕を振れます。
着地の際は、膝下が床と垂直になるよう意識しましょう。かかとから強く着地すると衝撃が大きくなり、前に進む力も半減してしまいます。足裏全体でまっすぐ踏み込むイメージを持ち、中足部をしっかりつくことで、自然と前に進みやすい着地ができます。
ランニングフォームは、首や肩に余分な力が入っていないか、極端な猫背や反り腰になっていないかを定期的にチェックし、左右のバランスが均等になるよう意識しましょう。鏡や動画で自分の走りを客観的に確認するのも効果的です。
呼吸筋を鍛える
呼吸に関わる筋肉を鍛えて呼吸持久力を高めると、血流が促進されて酸素が全身に行き届くようになり、長距離でも楽に走れるようになります。
呼吸筋のストレッチの手順を紹介します。
1.鎖骨の下に両手をあて、少し下に押さえながら大きく深呼吸します。
2.頭の上で右手首を左手でつかみ、ゆっくりと左へ上半身を倒して側屈し、そのままの姿勢で大きく呼吸します。肋骨の間に空気を送り込むイメージを意識しましょう。逆側も同様に行います。
3.腰のお尻の上あたりに両手をあて、吸いながら背面で肘を寄せていきます。同時に腰をしっかり支えながら、少し後ろに反るようにお腹を伸ばします。
このように呼吸に負荷をかけることで心肺機能や筋力が向上し、深い呼吸が継続できるようになります。集中力も上がり、疲れにくい身体づくりにつながります。
筋トレをする
筋力アップを図ることで持久力を向上させたり、フォームをより安定させたりできます。マラソンに役立つ筋トレを3つ紹介します。
<太もものトレーニング:スプリットスクワットの手順>
1.両足を腰幅程度の間隔で前後に開き、後ろ足の踵は少し上げます。
2.前足のつま先と膝が同じ方向を向いていることを意識しながら、前足の腿が床と平行になるまで身体をまっすぐ下ろし、元の位置に戻します。
上半身がぶれないよう軸を意識し、前足の膝がつま先から出ないように注意しながら、5~10回×3セットを左右の足を入れ替えて行いましょう。
<腹斜筋のトレーニング:ヒップロールの手順>
1.仰向けに寝て、両手を真横に広げ手のひらを床につけます。両足を軽く上げ、膝下が床と平行になるようにします。
2.頭を軽く上げ、おへそをのぞき込むようにしながら、両膝を左右交互に倒します。
膝を倒す角度は、反対側の肩が浮かないぎりぎりのところを目安にし、左右交互に20回ずつ行いましょう。
<体幹のトレーニング:プランクの手順>
1.うつ伏せの状態から両肘を床につけ身体を持ち上げます。
2.両肘と両足のつま先を支点にして、頭からかかとまでのラインをまっすぐ保ちます。身体が傾いたり反ったりしないよう注意しましょう。
最初はできる範囲の秒数から始め、徐々に60秒キープできるようになりましょう。腹筋、太もも、臀部に力を入れ、視線は手の数十センチ先に向けることがポイントです。
走った後にストレッチする
走った後やトレーニング後にストレッチを取り入れ、疲労を取り除いて翌日まで持ち越さないことも大切です。10~15分程度かけてじっくり伸ばすことで、関節や筋肉の柔軟性が改善され、リラクゼーション効果により血流がスムーズになります。
<ヒラメ筋のストレッチの手順>
1.膝を開いて正座をした状態から片膝を立て、その上で両手を膝に添えて体重をかけてアキレス腱を伸ばします。
2.足の裏を床にしっかりとつけ、膝の上に体重をゆっくりとかけ、アキレス腱とふくらはぎがストレッチされた状態を20秒ほどキープします。
体重をかけるときは上体を膝の上に被せるようにし、足の裏を浮かせないようにしましょう。主にふくらはぎの深い場所にあるヒラメ筋を伸ばす効果が期待できます。
<太もも前側のストレッチ>
1.両足を伸ばして座り、両手を体の後ろについて、片足を曲げて座ります。
2.上体を後ろへゆっくりと倒し、曲げた方の太ももの前側がストレッチされるのを感じたら20秒ほどキープします。
柔軟な人は背中を床につけて行い、身体の硬い人は手や肘で身体を支えることで伸ばす強さを調節しましょう。
<太もも裏側のストレッチ>
1.両足を開いて座り、片足を内側に曲げます。
2.足の裏を反対側の足の太ももの付け根付近に当て、伸ばした足の太ももに両手を置き、その上にゆっくりと上体を倒します。
背すじを伸ばしたまま行い、太ももの裏側がストレッチされているのを感じたら20秒ほどキープしましょう。無理に胸を太ももにつける必要はなく、痛みを感じないところで止め、自分の強度で行うことが重要です。
マラソンで力を出し切るなら栄養にも着目しよう!

トレーニングやペース配分と同様に、栄養管理もマラソンのパフォーマンスを左右する重要な要素です。適切な栄養補給を行うことで、持久力の向上やコンディション維持、そして目標タイムの達成につながります。
ここでは、マラソンで力を発揮するために欠かせない栄養について解説します。
▼前日からの食事の摂り方について知りたい方はこちら
「【保護者向け】試合前日~当日の食事の摂り方・メニューを紹介!」
血中アミノ酸量を高めておく
マラソンのペースを維持するためには、血中アミノ酸量を高めておくことが重要です。長時間の運動では身体が糖質や脂肪、血液中のアミノ酸をエネルギー源として利用しますが、それらがなくなると筋肉を分解してアミノ酸を利用するようになります。この状態が続くと筋肉は損傷し、筋力の低下を招いてしまうため、コンディションに大きな影響が出てしまいます。
アミノ酸を食事から摂取しようとすると、消化不良や胃腸のごろごろとした不快感が出るため、アミノ酸単体で補給できるサプリメントなどを活用するのがおすすめです。
例えばMUGEN BIONICが提供するEAAレギュラーは、消化工程がないため素早く吸収され、運動前、運動中、運動後のいつでも摂取可能です。
ミネラルを補給して脱水を予防する
マラソン中は大量の汗をかくため、ミネラルが失われていきます。汗は単なる水ではなく、ナトリウムやカリウム、カルシウム、鉄といったミネラルを含んでいます。体重の1%の汗で運動機能は約10%低下するとされ、3%では30%ものパフォーマンス低下につながります。
脱水状態になると足がつったり、体調不良でリタイアしたりと、競技に大きな影響が出てしまうこともあります。
そのため、トレーニング中や競技中に効率的にミネラル補給をしましょう。MUGEN BIONICでは、トレーニング中のミネラル補給に最適なミネラルパウダー Gazelleを提供しております。糖質控えめな設計なので、身体づくりに取り組むアスリートの方にもおすすめです。
まとめ
マラソンで理想の結果を出すには、自分に合ったペース配分を見極め、日頃のトレーニングと栄養管理を通じて安定した走りを実現することが重要です。イーブンペースを基本に、フォーム改善や筋力強化、適切な補給を取り入れながら、自分に最適な戦略で挑戦していきましょう。