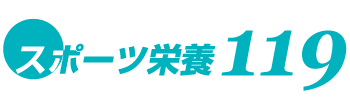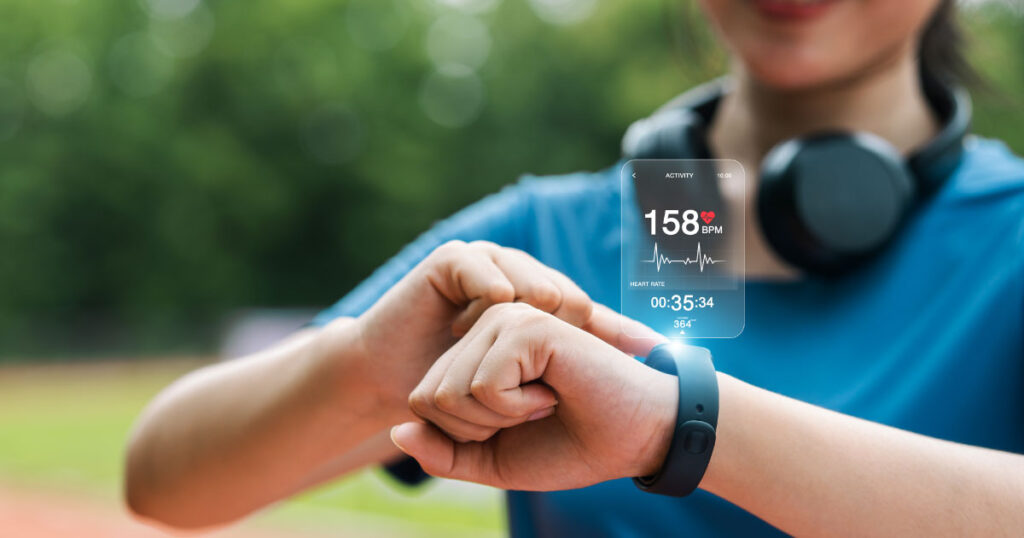
フィットネストラッカーでランニング中の心拍数を確認してみたら、予想より高い数値が出て驚いた経験はありませんか?心拍数が高く、「早く疲れてしまう」「目標距離を達成できない……」という悩みを抱える方も多いでしょう。
適切な心拍数ゾーンを理解し、高強度トレーニングと栄養管理を組み合わせることで、同じペースでも心拍数を抑えながら走れるようになります。
今回は、心拍数が高くなりすぎる問題の解決策と、効率的に心拍数を下げるための具体的な方法を紹介します。
Contents
ランニングで心拍数が高くなりすぎるとどうなる?
ランニングで心拍コントロールがうまくできないと、疲れやすくなったり、酸素が取り込みにくくなったりします。
それぞれのメカニズムを解説します。
疲れやすくなる
心拍数が高すぎる状態でのランニングは、通常よりも早く疲労を感じる原因となります。
これは、「LT値(乳酸性閾(いき)値)」(血中の乳酸濃度が2~4mmol/l)を超える可能性があるためです。
乳酸は、かつては「疲労物質」といわれていましたが、現在では筋肉などのエネルギー源であるとされています。
しかし、「LT値(乳酸性閾値)」を超えると血中の乳酸濃度が急激に増加しはじめ、分解(エネルギーへの変換)が追いつかなくなってしまうのです。このポイントが、最大心拍数(※)の約85%に相当するといわれています。
乳酸が蓄積すると筋肉内のpH値が酸性に傾くことがわかっており、これが疲労を感じやすくなる原因です。
※最大心拍数:人が発揮できる最大の心拍数のこと
酸素が取り込みにくくなる場合がある
心拍数が過度に高い状態では、息切れや呼吸困難が生じるなど、酸素の取り込みが困難になることがあります。
これは最大酸素摂取量(VO2max)の70~80%を超える高強度な運動によって引き起こされる現象です。
血流が速すぎることで酸素と二酸化炭素の交換がうまくいかなくなったり、呼吸が追い付かず血流への酸素供給が不十分になったりすることが主な原因となります。
出典:片山 敬章,他「10週間の最大インターバル トレーニングが高強度運動中の動脈血酸素飽和度に及ぼす影響」体力科学,1996,45(1),p219-226
ランニング中の適正な心拍数
ランニング中の適正な心拍数は、運動の目的や強度によって異なりますが、一般的に最大心拍数の50〜85%の範囲で設定されます。
まずは自分の最大心拍数を把握し、それを基準に目標心拍数を決めることが重要です。
最大心拍数は「220-年齢」で簡単に計算できます。
例えば30歳の方なら190拍/分、40歳の方なら180拍/分が最大心拍数の目安となります。
フィットネストラッカーで確認した心拍数が予想より高い場合は、現在の運動強度が自分の目的に適しているかを見直してみましょう。
運動強度別の適正な心拍数
アメリカ心臓協会の基準によると、運動強度別の適正な心拍数は以下のように分類されます。
・中程度の運動:最大心拍数の50〜70%
会話をしながらでも走れる程度で、長時間の運動が可能です。初心者の方や健康維持が目的の場合は、この範囲での運動がおすすめです。
・激しい運動時:最大心拍数の70〜85%
息が上がりやすく、会話は困難になりますが、心肺機能の向上や体力アップに効果的です。ただし、この強度で長時間運動を続けると疲労が蓄積しやすいため、適度な休息を取りながら行うことが大切です。
出典:アメリカ心臓協会(AHA)「目標心拍数チャート(Target Heart Rates Chart)」
目的別の適正な心拍数
ランニングの効果を最大化するには、目的に応じた心拍数ゾーンで運動することが重要です。ゾーン1から5まで、それぞれ異なる効果が期待できます。
・ウォーミングアップ:ゾーン1(最大心拍数の50〜60%)
軽く汗ばむ程度の運動で、体脂肪をエネルギー源として効率良く燃焼できます。
・脂肪燃焼:ゾーン2(最大心拍数の60〜70%)
この強度では脂肪燃焼が期待でき、日常的なランニングの基礎体力を築けます。
・持久力の向上:ゾーン3(最大心拍数の70〜80%)
持久力トレーニングでは、ゾーン3以上を目指します。関節を痛めやすい人やランニング初心者が注意すべきペースです。
・スピード耐久力の向上:ゾーン4(最大心拍数の80〜90%)
身体が厳しいと感じる強度です。レースペースでの運動を維持する力が高まります。
・瞬発力・運動能力向上:ゾーン5(最大心拍数の90〜100%)
最大強度で、心臓や血液循環、呼吸器系が最大限に発揮されている状態です。短時間での実施に留め、長時間の継続は避けるようにしましょう。
ランニング中の心拍数を下げる方法
ランニング中の心拍数を下げるには、心肺機能の強化と心臓の弾力性アップが重要です。そのために役立つトレーニングと、おすすめの栄養素を紹介します。
心肺機能の強化|ゾーン4~5のトレーニング
最大心拍数の80〜100%となるゾーン4〜5でのトレーニングを取り入れましょう。
高強度トレーニングにより心肺機能が向上すると、乳酸が蓄積し始める「LT値」も高くなり、息切れもしにくくなります。
おすすめのトレーニング方法としては、以下があげられます。
・きつめのサイクリングや水泳
・サーキットトレーニング
・インターバルトレーニング
・クロスフィットトレーニングなど
これらの高強度トレーニングはすぐに疲労が出るため、週2〜3回を上限として、十分な休養を取ることが大切です。
心臓の弾力性アップ|エラスチンの摂取
心臓の弾力性を向上させるには、エラスチンの摂取が効果的です。
エラスチンとはたんぱく質の一種で、血管や組織などの伸縮性を保つのに必要な弾性線維です。
特に、心臓から血液を体内に送る動脈には、エラスチンがたくさん含まれていることがわかっています。
しかし、年齢を重ねるとエラスチンは徐々に壊れてしまい、その働きが弱まります。その結果、血管の弾力性が失われ、心臓が高い心拍数に対応しづらくなることがあります。
一方、エラスチンがしっかり機能していれば、動脈は柔らかさを保ち、高い心拍数にも無理なく耐えられるようになります。
エラスチンを手軽に摂取するなら、「食べるストレッチ スポコラ」をおすすめします。
動脈の弾力性を保つのに必要なエラスチンとコラーゲンを配合しているほか、靭帯、腱、筋膜などをサポートする成分が含まれており、ランナーのケガ予防も期待できます。
詳しくは、以下のリンクからご覧ください。
また、エラスチンの効果については、以下のコラムで詳しく解説しています。
高負荷なトレーニング後の効果的なリカバリー方法
心拍数を下げるための高強度トレーニング後は、十分なリカバリーが不可欠です。
適切な回復を行わないと、疲労が蓄積して次回のトレーニング効果が低下したり、ケガのリスクが高まったりする可能性があります。
効果的なリカバリーの基本は、水分摂取、十分な休息、そしてアミノ酸を中心とした栄養素の摂取です。
アミノ酸は、たんぱく質の構成成分であり、消化を必要とせず、すぐに吸収されるため、疲労回復の即効性が高いのが特徴です。運動直後や運動中にも摂取でき、トレーニング後の疲れを早期に軽減できます。
アミノ酸を効率的に摂取したい方は、「EAAレギュラー」をぜひお試しください。高濃度のアミノ酸パウダーで、効率的な代謝を促し、疲れにくい身体づくりをサポートします。
また、アミノ酸の重要性についてさらに知りたい方は、以下のコラムをご覧ください。
「トレーニング後のプロテインはNG!EAA・BCAAとの違いは?」
【補足】ランニング中の心拍数が低い「スポーツ心臓」について
アスリートが運動中でも心拍数が低い現象を「スポーツ心臓」と言いますが、聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
スポーツ心臓とは、継続的な運動によって心臓が適応変化を起こし、運動時でも心拍数が低く保たれる状態を指します。
心臓が大きくなることで一回の収縮で送り出せる血液量が増加し、結果として同じ運動強度でも心拍数を低く保てるようになります。
スポーツ心臓は通常、生理的適応として健康的な現象と考えられており、運動をやめると2〜3年ほどで元の状態に戻ることが多く、その場合は危険ではありません。
しかし、過度なトレーニングや心臓に負担をかけすぎると、病的な心筋症などとの区別が難しくなることがあります。
そのため、心拍数を下げたいからといって無理な高強度トレーニングを続けることは避けましょう。適切な負荷と十分な休息を組み合わせることが重要です。
まとめ
ランニング中の心拍数を効率的に下げるには、週2〜3回の高強度トレーニングと十分なリカバリーを組み合わせるのが効果的です。エラスチンやアミノ酸などの栄養素も積極的に摂取しましょう。
フィットネストラッカーを活用して心拍数をモニタリングしながら、段階的に強度を調整し、無理のないトレーニングを心がけてください